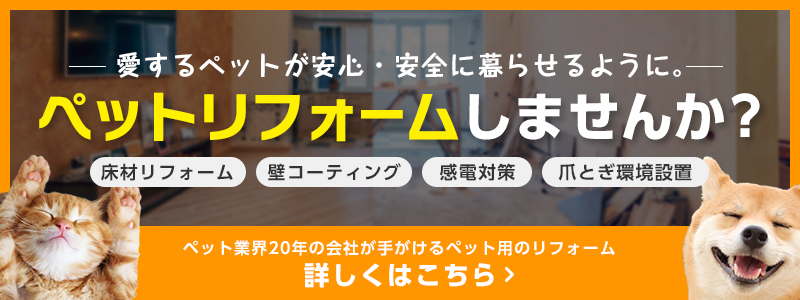犬を家族として迎えるということは、楽しみと同時に命を預かる責任が伴います。
可愛さだけで飼い始めてしまうと、思わぬトラブルや飼育放棄につながることも。
本記事では、犬を飼うときに知っておきたい注意点や必要な準備、心構えまでを分かりやすく解説します。
Instagram:わんにゃん家具【PetRide公式】
犬を飼うときの10の注意点
犬を迎える際は、環境や健康・登録など多くの準備が必要です。
飼う前に自治体へ確認しておく
犬の飼育には、地域ごとに異なるルールが設けられています。
集合住宅での飼育制限をはじめ、登録方法や届出の流れなど、細かな方法も自治体によって異なります。
実際に犬を迎える前に、市区町村のホームページや役所で「犬の飼育ルール」を確認しておきましょう。
特にマンションやアパートの場合は、ペット可と記載があっても犬種や体重制限などもチェックしておくことが大切です。
飼い主登録と狂犬病予防接種を行う
犬を迎えたら、30日以内に自治体へ「畜犬登録」を行う必要があります。
登録後に交付される鑑札は、首輪につけておかなければなりません。
また、狂犬病の予防接種は毎年1回ずつ受けることが法律で義務付けられています。
登録や注射済票の手続きは、自治体または動物病院で行えます。
室内飼いの環境を整えておく
近年は衛生面や安全性の観点から、室内での飼育が基本です。
犬が落ち着けるベッドやすべりにくい床、いたずら防止のコンセントカバーなどを用意しましょう。
また、夏は熱中症、冬は低体温症を防ぐため、エアコンを使った温度管理が必須です。
特に子犬や老犬は体温調整が難しく、ちょっとした気温の変化で体調を崩すことがあるため注意が必要です。
フードと食器をそろえる
犬の年齢・体重・健康状態に合ったドッグフードを準備します。
子犬と成犬、シニア犬では最適な栄養バランスが異なるため、飼い犬の状態に合わせて種類や量を調整することが大切です。
フード皿や水皿はすべりにくい素材を選び、常に清潔な状態を保ちましょう。
アレルギーの恐れがある場合、獣医師と相談のうえ療法食を選ぶと安心です。
トイレの場所を決め用意しておく
トイレトレーニングをスムーズに行うためには、最初からトイレの場所を固定しておくことが大切です。
ペットシーツやトレイを使って、人の動線から少し離れた場所に設置するのがおすすめです。
トイレが成功したときはしっかりと褒め、失敗しても叱ることなく、根気強くトレーニングするとうまくいきやすいでしょう。
おさんぽグッズを準備しておく
犬にとっての散歩は、運動だけでなく「外のにおいを嗅ぐ」「ほかの人や犬に会う」といった社会的刺激の場でもあります。
リード・首輪(またはハーネス)・うんち袋・おしっこを流す水などを用意するとともに、夜間は光る首輪やライトを使うと安全です。
散歩デビューの際は、ワクチン接種が完了したことを確認してから行うことも大切です。
健康管理と病院選びをしておく
犬の健康を守るためには、信頼できる動物病院を見つけておくことが大切です。
定期的なワクチン接種やフィラリア予防、ノミ・ダニ対策などさまざまな点に注意しなければなりません。
年に1回の健康診断を習慣化し、異変に素早く気が付けるような工夫を心掛けましょう。
持病がある犬の場合は、病院に情報を共有するとともに、万が一のトラブル時にどうすべきかシミュレーションを重ねておくと安心です。
トリミング・爪切り・耳そうじのグッズを用意しておく
トイプードルやシーズーといった毛が伸びやすい犬種は、1~2ヶ月に1回のトリミングが必要です。
また、爪が伸びすぎると歩行に支障が出るため、専用の爪切りを使って定期的にカットします。
耳そうじ用のシートやブラシなどもそろえておくと便利です。
留守番対策をしておく
犬は長時間の留守番が苦手です。
外出時には、安全なおもちゃや飼い主の声が聞こえる留守番用カメラなどを用意し不安を軽減するのがおすすめです。
また、エアコンの設定温度を調整し、室温を一定に保ちましょう。
誤飲・誤食防止のため、コードや小さなパーツのあるものは手の届かない場所へ移動することも大切です。
迷子対策をしておく
首輪には必ず迷子札をつけ、名前と電話番号を明記します。
また、「動物の愛護と管理に関する法律」では、2022年以降に販売される犬猫へのマイクロチップ装着が義務化されています。
該当年以前に飼い始めた犬や、譲り受けた犬などを迎える場合も、任意で登録しておくと安心です。
犬を飼う前に知っておくべき心構え3つ
犬を飼う前には、アイテムの準備だけでなく、家族全員の同意と協力体制を整えておくことが大切です。
一生を共にする覚悟を持つ
犬の寿命は平均で10年~15年ほど。
生活環境の変化や引っ越し、出産、介護などがあっても、最後まで責任をもって世話を続ける覚悟が必要です。
途中で「思っていたより大変」だと感じても、命ある家族の一員として向き合いましょう。
家族全員の合意を得る
家族のなかで一人だけが乗り気でも、日常の世話やしつけは家族全員の協力が欠かせません。
「散歩は誰が担当するか」「旅行のときはどうするか」などを事前に話し合い、全員が納得したうえで迎えることが大切です。
食事の世話や散歩、通院などは日常的に行う必要があるため、役回りを分担しておくのもおすすめです。
犬を飼うことの責任を理解する
犬を迎えると、食費やワクチン代、トリミング費用など継続的な費用がかかります。
また、病気や怪我をしたときには高額な医療費が発生することもあるため、ペット保険への加入も検討しましょう。
しつけやトレーニングなども必須であるため、子どもを育てるのと同等の責任が必要であると理解することが大切です。
犬を迎え入れた後の注意点3つ
実際に犬を迎えたあとは、以下に挙げた3つの点について十分に注意しましょう。
新しい環境に慣れさせる方法
犬を家に迎えた直後は、不安や緊張で落ち着かないことがあります。
最初の数日は静かで安全なスペースを確保し、無理に構わず見守る時間を設けましょう。
大勢で急に囲むのではなく、家族が交代でさりげなくそばにいてあげることで、犬も少しずつ新しい環境に慣れていきます。
初期の健康チェックと予防接種
犬を迎えたあとは、なるべく早く動物病院で健康状態をチェックすることが大切です。
便検査やワクチン、フィラリア予防など、獣医師の指導のもとで検査のスケジュールを立てることが大切です。
特に保護犬を迎えたときは、感染症の有無を確認しておきましょう。
トイレトレーニングの進め方
トイレトレーニングは、「褒めて伸ばす」が基本です。以下のポイントをおさえ、焦らず犬のペースで進めましょう。
- 心地よく使えるトイレを用意する
- トイレの場所を固定する
- 成功したらとにかく褒める
- 時間がかかっても根気強く教え続ける
- 粗相しても怒らない
- 常にトイレを清潔にする
犬のストレスになるやってはいけないこと
犬がストレスを感じると、自然としぐさや行動に現れます。
飼い主が無意識にとっている行動が、犬にとって負担になっている可能性も。
以下に挙げた一例に加え、日頃から犬の様子に変化がないか確認することが大切です。
大きな声で怒る・叩く
たとえ悪さをしても、犬を叩いたり怒鳴ったりしてはいけません。
恐怖心が強まり、飼い主への信頼を失ってしまいます。
正しい行動をしたときにしっかりと褒める「ポジティブなしつけ」を心掛けましょう。
犬は飼い主の表情をよく見ているため、笑顔で厳しい言葉をかけるのもよくありません。
表情と声のギャップが混乱を招き、犬が不安を感じてしまいます。
急な環境の変化を繰り返す
頻繁な引っ越しや模様替え、留守番時間の急な増減といった生活リズムの乱れは、犬に大きなストレスを与えます。
なるべく一定の時間に食事・散歩・就寝ができるよう、生活リズムを整えることが大切です。
スキンシップを嫌がっているのに続ける
人間が大好きな犬ですが、「今はかまってほしくない」というタイミングがあります。
しっぽを下げていたり、身体を反らして嫌がったりしている場合は、無理に触れず距離をとらなければなりません。
おさんぽをサボる・自由に動けない生活
散歩は、身体はもちろん犬の心を健康的に保つためにも大切な時間です。
忙しいからといって散歩を減らすと、ストレスを感じるだけでなく、吠えたり噛んだりといった問題行動にもつながります。
まとめ
犬を飼うことには、喜びと同時に命を預かる責任が生じます。
「可愛いから飼う」だけでなく、「最期までともに生きる」といった覚悟をもって、大切な家族を迎え入れることが大切です。