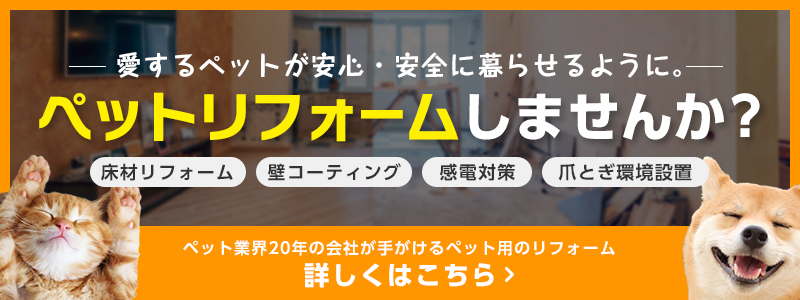犬の甘噛みは飼い主なら可愛いと感じるものですが、放置すると本気噛みに変わってしまうなどさまざまなリスクがあります。
本記事ではそんな犬の甘噛みをしつける方法や、そもそもなぜ甘噛みをしてしまうのかといった理由についてご紹介します。
Contents
犬が甘噛みをする理由
犬の甘噛みはある程度の時期にしつけた方が良いとされていますが、そもそもなぜ甘噛みをしているのか考えたことはあるでしょうか。
まずは犬がなぜ甘噛みをするのか、考えられる理由をピックアップしてご紹介します。
子犬期
子犬期に起こる甘噛みは、歯が生え替わるタイミングで口の中がムズムズしていたり、おもちゃをかみかみするような感覚で飼い主の手を噛んでしまったりといった原因が考えられます。
そのほかにも、歯で噛むことでものの硬さや質感を確かめていたり、「噛んだらどうなるんだろう」「飼い主はどんな顔をするだろう」と試したかったりするケースが考えられます。
この時期に正しいしつけをすることで、犬は噛んで良いものと悪いものを覚えていくでしょう。
単に全てを噛まないよう注意するのではなく、噛んでも良いおもちゃを与えてストレスを発散してもらうこともおすすめです。
成犬期
成犬期に起こる甘噛みは、遊びでテンションが上がり楽しくて噛んでしまったり、本気噛みと区別することで飼い主への愛情をを伝えたりするものです。
成犬とはいえ甘噛みはほぼ痛みがなく、相手を思いやりながら噛んでいることが分かるでしょう。
遊びの延長でつい強めに噛んでしまったときは、必ず目線を合わせて座り、痛かったことを正面から伝えてあげることが大切です。
まだ、ストレスが溜まった子が、おもちゃや飼い主の服などを噛むことで解消している可能性も考えられます。
留守番の間に噛んでしまったり、噛んだものを隠したりする子もいますが、決して怒らずにストレスの原因を探ってあげましょう。
犬の甘噛みを放置するリスク

犬の甘噛みは時として非常に可愛らしいものですが、放置してしまうとさまざまなリスクが高まります。
実際にしつけを始めてもすぐに効果が出るわけではないため、早めの対処をするためにも、甘噛みのリスクについて正しく知っておきましょう。
本気噛みへのエスカレート
甘噛みをしても飼い主が何もいわないと感じると、犬はさらに噛む力を強めることがあります。
特に飼い主からかまってほしくて噛んだ場合、「もっと強くすればきっとかまってくれるだろう」と考え、本気噛みをしてしまう子もいるでしょう。
甘噛みだからといって「かわいいね」と褒めず、「噛んではいけない」とストレートに伝えることが大切です。
家具や物への被害
たとえ甘噛みであろうと、犬の顎の力を見くびってはいけません。
飼い主の手がないときに家具や物を噛んでしまえば、すぐにボロボロになってしまうはずです。
犬を飼う上で不要なもの・危ないものは手の届かないタンスにしまったり、壁やソファなどを専用のシートで覆ったりしておくと安心です。
動物病院での診察が受けられない
甘噛みや本気噛みが多い子は、動物病院で医師やスタッフを傷つける可能性があり、安易に診察を受けられなくなってしまいます。
しつけ自体を動物病院で相談することも良いですが、他の体調不良で病院にかかるときのことも考え、なるべく早くしつけを開始すると良いでしょう。
関連記事:一人暮らしで犬を飼いたい方必読!おすすめ犬種と注意点
犬の甘噛みはいつまでにやめさせる?

犬は種類や個体によっても異なりますが、主に生後3ヶ月頃を目安に甘噛みをするようになります。
この頃にすぐしつけをした場合は、甘噛みをやめることが容易であり、飼い主や他の人を傷つける心配が少ないでしょう。
もちろん人間の子のように「やめて」と言ってすぐに理解できるわけではないため、この後ご紹介するしつけの方法も併せてチェックすることが大切です。
生後1年を超えてくると、成犬期に入ります。これ以降の犬は甘噛みをしつけることが難しく、噛み癖が残ってしまう場合があるでしょう。
とはいえ成犬でもまったくしつけができないわけではないため、決してあきらめてはいけません。
まずはどうして甘噛みをしてしまうのか、強く噛んでしまったときに何を訴えたいのかを考え、次でご紹介するしつけへつなげていきましょう。
関連記事:犬を飼うのに向いているのはどんな人?
犬の甘噛みをしつける方法

続いて、実際に犬の甘噛みをやめさせるために取り組んでほしいしつけの方法についてご紹介します。
子犬期と成犬期ではアプローチが異なるため、年齢に合った方法を選びましょう。
子犬期のしつけ方
子犬の甘噛みをやめさせる際は、決して声を荒げることなく、犬が分かりやすいシンプルな言葉で牽制することが大切です。
「だめ」「ノー」など聞き取りやすい言葉を選び、しつけのたびにワードを変えることなく最後まで貫きましょう。
こうすることで甘噛みがいけないことだと分かるほか、他で悪さをしたときも、同じ言葉に気が付いてすぐにやめられるようになります。
また、犬がなぜ怒られているのかを忘れないため、甘噛みをしたときはすぐにしつけを行わなければなりません。
後から悪い点を指摘しても、具体的にどの行動を叱られているか分からず、改善には繋がりません。同じ理由で、犬を褒めるときも直前に声掛けをするようにしましょう。
成犬で噛み癖が残ってしまった場合の対処
成犬で噛み癖が残ってしまった場合も、基本的には子犬へのしつけ同様、短い言葉で牽制を行います。
その他にも「待て」や「静かに」といったコマンドを覚えさせ、甘噛みをしようとしたタイミングで止めることも良いでしょう。
こちらも必ず行動のすぐ後にしつけを行い、後回しにしないことが大切です。
成犬の場合、甘噛みをすることで飼い主がかまってくれると思っている子も少なくありません。
甘噛み自体を止めさせるだけでなく、根源であるストレスを解消してあげましょう。
少し長めに散歩をしたり、ドッグランでフリスビーをしたりと、身体を動かすストレス発散方法がおすすめです。
ペットとの快適な暮らしをリノベーションで実現!
長年ペット業界に携わってきたペットライドでは、新たに犬を迎えるお客様の自宅をリフォームし、お互いに住みやすい環境づくりを提供しています。
参考までに、実際にペットリノベーションを行った方の感想をご紹介します。
【高橋一郎さん】
「うちの家に合わせた特別な脱走防止ゲートがとても効果的で、犬が家から出ることがなくなりました。」
【中島達也さん】
「一度お隣さんからクレームを言われてから犬の吠え声が心配でしたが、防音リフォームで周囲に迷惑をかけずに済んでいます。家族もペットもストレスフリーです。」
ペットリノベーションといってもその内容は家庭によって様々であり、運動しやすい部屋にしたい場合や匂いを抑えたい場合・鳴き声で周りに迷惑がかからないようにしたい場合などお客様の希望も多種多様です。
こうした声に一つひとつオーダーメイドで対応できるペットライドだからこそ、犬との新しい生活を安心して迎えられるでしょう。
まとめ
犬の甘噛みはそれほど痛みを感じませんが、エスカレートすると良いことがありません。
飼い主だけでなく周りや公共の場での影響を考え、早い段階からしつけを行うと良いでしょう。
甘噛みをしたからといって大騒ぎせず、まずは冷静に「だめ」と伝えながら、同時に犬のストレスを解消してあげることが大切です。