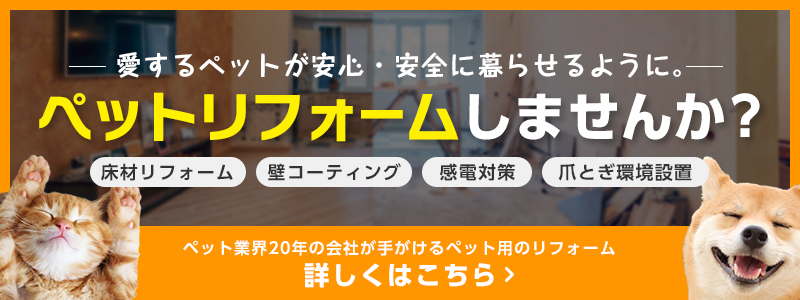かねてから憧れていた犬をお迎えするとき、ふと「自分は犬を飼うのに向いているのか」と考えたことがある方も多いのではないでしょうか。
せっかくお迎えしたにも関わらずお互いに不都合なことが起きないよう、事前に犬を飼うときの適性についてチェックしておきましょう。
犬を飼うのに向いているのはどんな人

本来、犬を飼うのに「向いている」や「向いていない」はなく、愛情を込めてお世話ができるのであれば誰でも一緒に暮らすことができます。
とはいえ、犬を飼う際は様々な点に注意する必要があり、いくら愛情があってもなかなかうまくいかないこともあるでしょう。
まずはこれからご紹介する3つのポイントを参考に、自分が犬との暮らしに向いているかどうか判断するところから始めましょう。
時間とお金に余裕がある人
犬は食事だけを提供すれば良いわけではなく、一緒に触れ合ったり、健康診断やワクチン接種などで病院にかかったりと、人間の子育てと同じような生活が待っています。
自分のことがおろそかになるほど時間に余裕がなかったり、犬の食事やペットシーツなどのアイテムにお金をかけられない場合は、無理してお迎えしない方が良いかもしれません。
強行突破して犬をお迎えしても、時間やお金を切り詰めて生活しなければならず、犬にとっても飼い主にとってもストレスが溜まってしまいます。
責任感が強く愛情深い人
犬は人間のことを良く見ており、信頼できると判断した相手に対して初めて心を許してくれる生き物です。
猫は場所に、犬は人に懐くといわれており、飼い主の性格によっては犬となかなか打ち解けられないことも多いでしょう。
特に責任感が強く、愛情表現が豊かな人は、犬も自分に対する愛情を理解しやすくスピーディに打ち解けやすいといえます。
アクティブなライフスタイルの人
身体の大きさによって時間や距離が異なりますが、ほとんどの犬が定期的な散歩を必要とします。
時間に余裕がある方はもちろん、身体を動かすことが苦ではない方が犬との暮らしに向いているといえるでしょう。
大型犬や活発な犬種は飼い主も一緒になって走ることもあり、運動不足解消を目指している方にもおすすめです。
また、日々の散歩だけでなく、時にはドッグランなどに出かけてみることも必要です。
他の犬と触れ合いながらストレスを解消していくため、飼い主同士もコミュニケーションを取る場面が出てくるでしょう。
こうした意味も含め、元々アクティブなライフスタイルを好む方の方が、犬をお迎えしたときの大変さを感じにくいといえます。
犬に懐かれやすい人の特徴

同じ家で生活をしていても、犬に懐かれやすい人・そうでない人が存在します。
せっかくならば犬に懐かれやすい人になりたい、と思っている方も多いのではないでしょうか。
続いては犬から好かれるためのポイントを5つご紹介しながら、犬に好いてもらうための工夫を学んでいきましょう。
犬が好む触れあい方を理解している
犬が人間との触れ合いを好む生き物だとはいえ、乱暴に触れたり、犬を下に見るような言動があったりする場合は本当の意味で分かり合うことはできません。
犬に敬意を払いながら、目線を合わせて犬から近づいてくれるのを待ちましょう。
間違っても不意に顔の前へ手を出したり、しっぽやお腹などのデリケートな部位に触れたりしてはいけません。
犬であっても一人の人間のように敬意をもって接することが大切です。
優しく穏やかな雰囲気を持っている
明るく楽しい性格の方は犬と楽しく過ごすことができますが、大きな声を出したり、大勢で騒ぐ時間が長かったりすると犬も疲れてしまいます。
楽しむときは楽しむ、休むときは休むといったメリハリを大切にしながら、普段は優しく穏やかな雰囲気で接してあげると良いでしょう。
犬も飼い主と楽しく遊びたいと思っていますが、ときにはゆっくりとリラックスして過ごしたいもの。
特に家の中では心から安らげるよう、ゆっくりとした口調を心掛けたり、激しい物音を立てないように工夫したりすることをおすすめします。
落ち着いた態度をとっている
普段から声を荒げることなく、落ち着いた態度をとっていると、犬から好かれやすくなります。
犬は人間の何倍もの聴覚を持っているため、急な大声・物音に対し敏感に反応してしまいます。
先ほども触れたように楽しむときは思い切り楽しみ、普段は落ち着いて過ごせる人ならば、犬も心からリラックスして過ごせるはずです。
適切な距離を保つ
人間のことが大好きな子も多い犬ですが、四六時中ベタベタと触れ合っていると、自分の時間が取れずにストレスが溜まってしまいます。
特に慣れていない最初のうちは、適切な距離感を保てるように工夫しましょう。
何の前触れもなく身体に触れたり、急に近づいたりすることなく、徐々に距離を縮めていくことが大切です。
特に多いのは、幼い子どもが距離感を掴めず、いきなり犬に触れてしまうケースです。
犬は賢いため幼い子を「幼い」と理解していますが、それでも嫌な気持ちを抑えることができずに反発してしまう子もいます。
子どもであっても大人であっても、犬を一人の人間として扱い、徐々に仲良くなっていくことを目標にすると良いでしょう。
自然な体臭で嫌なにおいがしない
犬は人間の何倍も鋭い嗅覚を持っているため、体臭には敏感に反応してしまいます。
特に柔軟剤や香水などの強すぎる香りを苦手とする子が多いため、犬と触れ合うときはこうした香りを避けておくと良いでしょう。
もちろんしっかりとお風呂に入って清潔さを保つこと、体臭のきつくなるような食べ物はなるべく食べないよう注意することも大切です。
犬が嫌がるのはこんな人

続いて、犬が嫌がる人の具体例を参考に、犬と触れ合うときのNG行為について学んでいきましょう。
急に犬から好かれることは難しくても、犬から嫌われたり、威嚇されたりするとこちらも悲しくなってしまいます。
事前にできる対策を行っておき、ストレスなく触れ合えるように準備しておくことをおすすめします。
大声を出す人
聴覚の鋭い犬にとって、急な大声はその人を嫌いになる大きな理由の一つです。
特にキャーッと叫ぶような高い声を苦手とする子が多く、子どもがいる家庭へ犬をお迎えする際は注意が必要となるでしょう。
犬がいる空間では急な大声をなるべく避け、落ち着いてゆっくりと話す工夫が大切です。
急な動きをする人
物事の変化に敏感な犬は、急な周りの動きにもすぐに反応してしまいます。
急な動きをする人が近くにいることで、終始落ち着かない時間を過ごすこととなるでしょう。
忙しいからとバタバタ動き回りながら家事を行ったり、家の中でも常に走り回っている子がいたりすると、犬がリラックスする時間を確保できません。
人工的な強い香りをまとっている人
先ほどもご紹介したように、犬は鋭い嗅覚を持っているため、強い香りを苦手としています。
特に柔軟剤や香水など、自然界にはない人工的な香りは苦手とする子が多いため、犬と触れ合う際は付けないように工夫しましょう。
特に柔軟剤は長年使っているうちに慣れてしまい、人間の鼻では違和感を覚えないことも多いため、無香料のものにするなどの対策が必要です。
目をじっと見つめてくる人
犬をはじめとする動物にとって、目をじっと見つめられることは、威嚇と捉えられる場合があります。
コミュニケーションを取ろうとして目を見つめた結果、却って唸り声を上げられてしまうこともあるでしょう。
慣れていないうちは犬の目をまっすぐに見ることは避け、少し目を逸らしながら徐々に距離を縮めていくと良いでしょう。
もちろん立った状態で上から手を伸ばすのではなく、同じ目線まで下がり、身体を小さく見せることも大切です。
無理に触れ合おうとする人
いくら飼われている期間が長いとはいえ、犬が野生の本能を完全に捨て去ることはありません。
いつでも周りに警戒心を持っている子もいるため、不用意に触れ合うことは避けましょう。
慣れていないにも関わらず無理に触れ合おうとすると、犬から嫌われてしまうだけでなく、噛みつかれたり引っかかれたりといった怪我をする恐れもあります。
関連記事:飼いやすい犬種ランキングを公開!初心者にもおすすめの犬種はどれ?
その他|犬を飼う前に考えたいこと

最後に、犬を飼う前にもう一度考えておきたいことを5つご紹介します。
「可愛いから」「仲良くなりたいから」といった単純な気持ちだけで犬をお迎えしてしまうと、お世話の大変さや懐くまでの時間の長さにがっかりしてしまう方もいます。
あらかじめ犬を飼う際の大変さや飼い主としての責任について学んでおくことで、最後までしっかりと添い遂げ、かけがえのない家族となれるでしょう。
ライフステージに合わせたケアができるか
一言で「犬のお世話」とまとめてしまいがちですが、ライフステージに合わせて適切なお世話の方法が異なります。
それぞれの時期に合わせたケアを行い、必要に応じて飼い主の生活スタイルを変えていくことが大切です。
子犬の頃は一日三食をしっかりと食べさせる必要があるため、昼間の時間帯に家を空ける方は向いていません。
危険がないかを確認するためにも、常に誰かがそばにいる状態を作ると良いでしょう。
反対にシニア犬の場合、慢性的な身体の不調が増えてくるため、自然と通院の負担が発生するようになります。
子犬同様に長く家を空けることはできなくなるため、仕事の調整が必要となることも多いでしょう。
安全かつ快適な飼育環境を提供できるか
犬はもちろん、どんなペットをお迎えする際も、安全かつ快適な飼育環境が必要不可欠です。
特に犬の場合は動き回る子が多いため、十分に運動できるスペースを確保してあげましょう。
そのほかにも、ゆっくりと食事ができるスペースや、人の目を気にせず排泄ができるトイレスペースなど、人間と同じく様々な生活環境が必要といえます。
犬種ごとの特性に応じた対応ができるか
一言で犬といっても、犬種によって特性に大きな違いがあります。
性格の違いはもちろんのこと、運動量の違いにも注目しておきましょう。
小型犬であれば1日1回の散歩で済むところ、大型犬の場合は1日2回、もしくは2時間以上の散歩が必要となることもあり、その分飼い主の体力や時間を消耗します。
また、身体を清潔に保つ必要があるため、お風呂やトリミングサロンの頻度も検討しておきましょう。
特に毛の長い種類は月に1回のトリミングが必要となることも多く、最寄りに店舗があるか、料金はいくらかかるかといったポイントにも注目しなければなりません。
短毛種の場合も定期的なシャンプーや爪切りなど日頃のケアが欠かせないため、こまめに犬の状態をチェックすることが大切です。
突発的な出費に対応できるか
食事やペットシーツなどの固定費のほか、急な怪我や病気などの突発的な出費に対応できるよう準備を整えておきましょう。
固定費だけでカツカツになってしまうと、いざというときに治療費を払えず大変な思いをすることとなります。
特にペットの場合は治療費が実費になることも多いため、日頃から費用を貯めておいたり、必要に応じてペット保険を検討したりすると安心です。
犬の最期を見届ける責任があるか
犬はペットの中でも長生きする生き物ですが、それでも人間よりはるかに寿命が短いという特徴があります。
どれだけ可愛がって生活していても、いつか来る最期の日を避けることはできません。
大切な命が失われることを日頃から覚悟しながら、最期まで責任をもって見届ける強い気持ちを持つことが重要です。
ペットがその命を終えるとき、飼い主は時折「ペットロス」に陥ってしまいます。
うつ状態になる方も多く、ペットの存在がどれだけ大きいものであったかが分かるでしょう。
最期の瞬間までその子が幸せであったと思えるように、与えられる最大限の愛情をもってお世話してあげる覚悟を持ちましょう。
まとめ
犬を飼うのに向いている人とは、人間の家族が一人増えたのと同じように、その子に対して時間やお金・労力、そして愛情をかけられるかどうかで決まります。
犬と過ごす時間がかけがえのないものになるように、犬にとっても、そして飼い主にとってもストレスが溜まらないような生活を心掛けましょう。